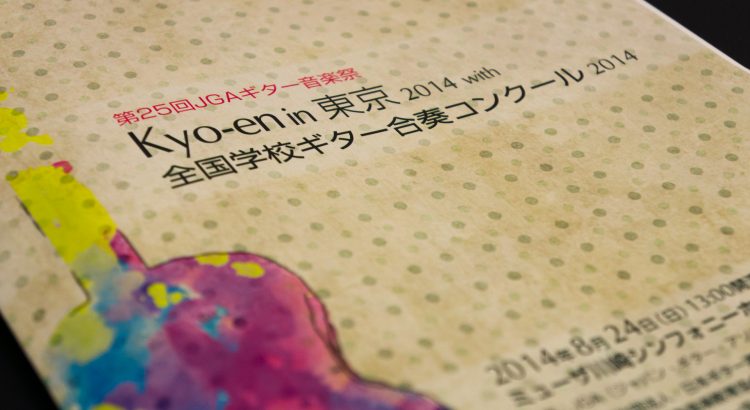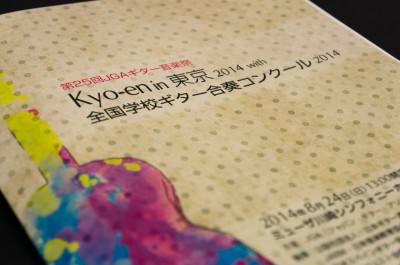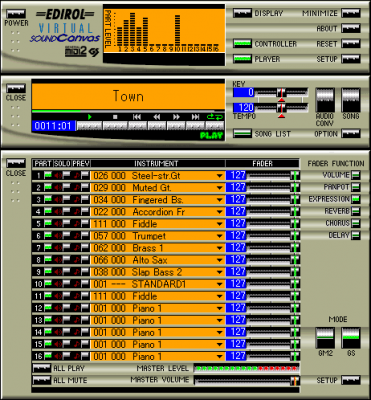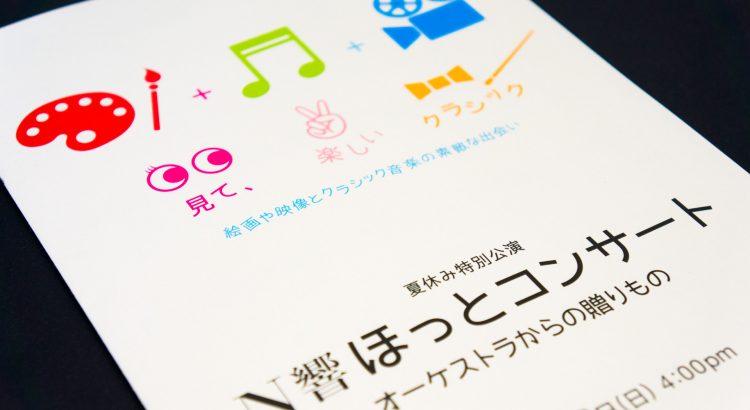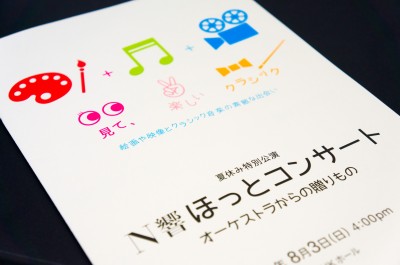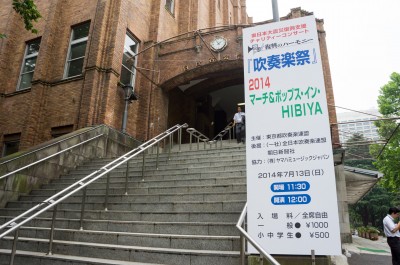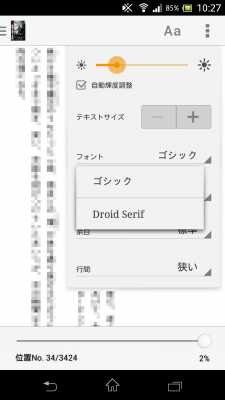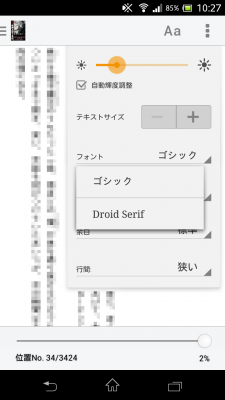全国学校ギター合奏コンクール 2014。併催、第 25 回 JGA ギター音楽祭 Kyo-en in 東京 2014。
今年もこの日がやってきた。
8 月 25 日、ミューザ川崎シンフォニーホール。前身の全日本学生ギターコンクールを含めると、ぼくの人生で十二年目のこのコンクール。年にいちどの夏の楽しみになって久しい。
行ってきたというとお客さんのようだけれど、実のところだいたい毎年、裏方のひとりとしてぼくは舞台袖に居る。
袖では見えない風景も、袖では聴けない音楽も、袖では味わえない空気もあるけれど、袖でしか見えない風景も、袖でしか聴けない音楽も、袖でしか味わえない空気もある。
ぼくはそういうものがだいすきで、だからぼくはぼくがそこに居られることがすごくうれしい。
会釈するだけ、ほんのひとことふたこと言葉を交わすだけ、あわただしく動き回っているとどうしてもそれだけしかかなわないこともあるのだけれど、それでも出場するいろいろな学校に、友人知人が居る。自分が出場していたころ、あるいはまだぼくの世界が狭かったころ、どうしたって母校びいきで、いうなれば “多摩とそれ以外” というくくりでしか観られなかった世界も、今ではもうまるで違うもの。
“やりたいからやる” という、人類最強のモチベーションの表出であるところの、部活。
全国にちらばるたくさんのそれが、コンクールとコンサートという似ているようで四分の三くらい対極にあるふたつをそれぞれで繰り返すわけで、どうしたって創発的に進歩するはずだし進化するはずだし発展するはずだし発達するはずで。年々レベルが上がっているとよく言われるけれど、だからある意味でそんなことは当たり前で、逆にそうでなければこの世界に未来はない。
順位が決まって、賞が決まって、今年のコンクールはそれで終わる。どこが勝った、どこが負けた、うれしい、くやしい、いろいろあるし、友人たちがわんわん泣いているのを観て、ぼくだっていろいろ思うけれど。
この日、この学校がこういう演奏をした。その演奏は、この審査員の方々にこう評価された。その結果、こういう順位が付いた。それはもうひとつの事実で、あしたからのギター合奏は、その事実の上でしかできないし、その事実からしか生まれない。あしたのギター合奏は、あしたをいきるひとがつくるし、一年後のギター合奏は、一年後をいきるひとがつくる。
ぼくが出ていた頃と今年のこれとを近似直線で結んでみたところで、この先の百年二百年の予測が立てられるわけでもない。それでも未来は過去がないとつくれないから、この日は未来のギター合奏を作るためには必要不可欠な一日で、それを演奏者として作り上げた七百名はやっぱり偉大な方々なのだと思う。出場することでしか得られないものは、溜め息がでるほどに大きいし、目眩がするほどに大きい。いくら裏で動いていようと、それはぼくには得られない。
これから、この世界はどうなっていくのかしらと、どういう未来がくるのかしらと、少しばかりの不安とともに大きな期待を持ちながら。できればぼくは、この世界の未来の姿を、自分の目と耳で観て聴いていたいと思う。
出場されたみなさま、よい音楽とよい時間をありがとうございました。
ぜひ、それぞれの人生を。