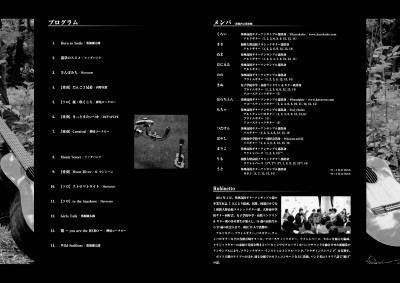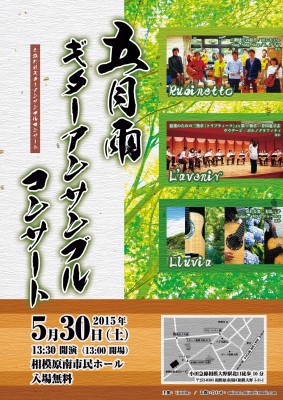だいたい一年前の コレ を最後にコンサートのまとめエントリ的なものを書かなくなってしまっていました。
単にそれどころではなくなった、というだけですが、中途半端なのも気持ち悪いからせめて 2015 年分はメモを残しておきます。
- ソニー吹奏楽団 第 51 回定期演奏会
- 6 月 27 日(土)練馬文化センター 大ホール
- libertas ライブ vol. 6 “ピアソラ × 日本の歌”
- 6 月 14 日(日)MFY サロン
- ARTE TOKYO 第 5 回定期公演
- 6 月 21 日(日)東京オペラシティコンサートホール タケミツメモリアル
- 某社某イベント
- 8 月 19 日(水)都内某所
- 全国学校ギター合奏コンクール 2015
- 8 月 22 日(土)東京芸術劇場 コンサートホール
- 向日葵ギターアンサンブルコンサート
- 8 月 29 日(土)和光大学ポプリホール鶴川
- イ・ムジチ合奏団
- 10 月 20 日(火)紀尾井ホール
- イ・ムジチ合奏団
- 10 月 24 日(土)サントリーホール
- JAGMO 伝説の音楽祭 – 勇者たちの響宴 –
- 10 月 25 日(日)新宿文化センター 大ホール
- サウザンドまつり
- 11 月 1 日(日)サウザンドシティ 多目的ホール
- ソニー吹奏楽団 ファミリーコンサート
- 11 月 3 日(火)大田区民ホール アプリコ
- 第 5 回 岡上分館カフェコンサート
- 11 月 28 日(土)岡上分館
- リード×シエナ ~リードイヤー・クライマックス!~
- 12 月 12 日(土)東京オペラシティコンサートホール タケミツメモリアル
- ギタークリスマスコンサート 2015
- 12 月 20 日(日)杜のホールはしもと
なんだかんだでいろいろ行っているっぽさがあるですね。
イ・ムジチ合奏団の公演に 2 回行けたのはすごくよかったです。ぜんぜん違うプログラムの日を選んだのでまるごとオイシイ感じでした。JAGMO は相変わらずイケイケでした。
2016 年は書きたくなったときだけ書くことにします。